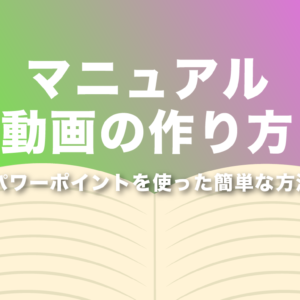CSR動画とは、ブランド力向上や価値の再創出のためにある動画です。
CSRとは、Corporate Social Responsibilityの略で企業の社会的責任を意味しています。
しかしこのCSR、大きな概念であり重要なワードではありますが、
現在CSRを取り巻く環境は大きく変化しており、
これらについて向き合い場合によってはすぐに変更していく柔軟な姿勢が求められるでしょう。
何故なら、社会はSNSを通じてグローバル化しており、
何かの力によるコントロールが世界的に無意味になってきたからです。
そして現在は、炎上が炎上を呼び起こす形となり、
過去の小さなリスクが炎上のガソリンとなっている傾向にあります。
この状況は今後より大きくなるでしょう。
インターネットを通じて発信される情報は全てログが残り、
誰かにより掘り起こしが行われれ、開示、再拡散されていきます。
CSRでは、炎上リスクを伴うセンシティブな要素を複数取り扱っており、
過去のCSRが炎上時の燃料になる可能性があることを忘れてはいけません。
これからのCSRについては、時代に合わせた修正と改善、新しいCSRを打ち出すと同時に、
過去のCSRについての振り返りと変遷の理由について説明していく必要があるでしょう。
これらは、変化する時代に合わせて企業を守りつつ、
よりよい企業としてPRすることになります。
何故、このようなことが必要になってくると予想されるのか。
現在、世界が取り巻いている炎上騒動などを例にあげながら、
CSRの価値、次ぎの時代のCSR動画について考えていきたいと思います。
企業の社会的責任とは
CSRの言う所の責任とは、どんなものなのでしょうか。
多くの場合、よく分からない中で、「サステナビリティ」や、
「雇用」「貢献」といったワードで判断しているのではないでしょうか。
CSRは抽象的です。CSRだけでは意味を成しません。
社会的責任は、別の誰かが定義する必要があります。
ですからCSRに意味はありません。
CSRを俯瞰して改めて定義するとすれば、
「定義した責任が社会(一般市民)が納得する内容になっているもの」
これがCSRなのではないでしょうか。
すると、大きな問題があります。
「社会が納得する内容」の部分です。
社会は常に変化しています。
ご存じの通り、意見は時代の変化によって簡単に反転し、覆ります。
大衆の意見に正しいはありません。
その時の感情が正しく、それが多ければ正義です。
このよな中では、CSRは非常に不安定なものであると考えられます。
CSRの価値
ここまで述べてきたことから考えるとCSRを定義することは、自らリスクをとることに他なりません。
一見すると無謀ですし、意味が無いように感じられます。
敢えて違う視点で考えてみると、だからこそCSRを定義することに意味があるようにも思えてきました。
SNSを通じて大衆や、社会が簡単に翻るのを多くの人が大なり小なり感じている時代です。
心のどこかで、次ぎは自分が間違えるのではなのではないか、という怯えもあるでしょう。
そんな中で率先してリスクをとりCSRを定義するのは、ある意味で非常に安心感があります。
この点から考えると、しっかりと内情や企業文化と合わせて設定されるCSRには意味があると感じます。
逆に言えば、流行や外的圧力に合わせて設定されたものは、
それが炎上のガソリンとなるネガティブ材料を自ら作り出してしまうことになりかねません。
なぜ、安易に定義したCSRが炎上時のガソリンとなってしまうのでしょうか。
DEIの失敗
DEIとCSRは多くの面で関連しています。
CSRは、企業の社会的責任をさしていますが、DEIはCSRの中にある、
社会的活動や人権に関わる部分と紐付いています。
そのためDEIの功罪について目を向けることで、
今後CSRの動向や企業に向けられている目や反応についても予測することができると、
推察しています。
その中で注目したいのがDEIの失敗です。
DEIとは、diversity, equity, and inclusionの頭文字をとたもので、
多様性と公平性について取り組みや価値観を表明することに使われています。
とは言え、最近では多様性の側面が強く、ポリコレ、トランスジェンダー、人種の違いという面の認識が強く、
またDEIをそういった団体が後援していることもあり、これらのワードに起因する問題の総称的な意味にもなっています。
そして注目すべきはアメリカの方針変換ではないでしょうか。
トランプ大統領によるDEIの終了です。
昨今のDEIブームは、一部の業界で大きな不評や経営的な失敗したことで、
DEIを重視した活動は世界規模でネガティブに映ってしまうようになりました。
このような時代の変化は非常に速く感じます。
DEIの盛り上がりがあったのは日本では、4~5年前程度ではないでしょうか。
たった5年での大転換です。
日本にこうった流れが本格的に伝わって来るまで3年は掛かる。
なんて事がありましたが、もうそれは時代遅れでしょう。
SNSが世界とを繋がったことで、世界の潮流も数ヶ月の時差しか生まないように感じます。
そのため、世界の潮流に合わせる必要がある。
海外に進出している大企業が、性関連の不祥事でCMの取り下げるなど素早い反応示しているのが証拠です。
悪い意味ではグローバルスタンダードは確率した状況と言えなくはありません。
ですので、DEIの問題で起こっている世界の反応や意識は日本でも同様に起こりえることで、
中小企業関わらず、日本と世界の両方の常識感に合わせた対応が求められるようになってくるでしょう。
DEIの問題でわかりやすいのが、UBIソフトが開発しているアサシンクリードシャドウズの問題です。
アサシンクリードシャドウズの問題
アサシンクリードとは、ユービーアイソフトが開発した、暗殺者をモチーフしたアクションゲームです。
アサシンクリードは爆発的な人気を誇り、シリーズ化されています。
その最新作であるアサシンクリードシャドウズというのが問題となりました。
アサシンクリードシャドウズは日本を舞台にしています。
戦国時代を舞台にしたゲームなのですが、歴史や著作の面で大きな問題を抱えています。
そして、その問題を大きくしているのがDEIの負の側面とグローバル化による弊害ではでしょうか。
一つ一つは紐解けば小さな問題かもしれませんが、現代ではその一つ一つの小さな問題までもが
炎上を起こせば火種となり、大きく長く燃えるようなことになってしまいます。
アサシンクリードシャドウズでは、歴史や著作の問題があります。
著作の無断利用については、AIの画像盗用などにかかっている可能性があり、問題が複雑になっています。
これらの問題は、今後世界的規模で影響を及ぼすことになるでしょう。
この点については、本内容から離れてしまいますが、今後の世界の流れを考えると、留意しておくべき事項です。
問題と炎上は別々で考えるべきですが、
炎上の原因の要因となっている一つにポリコレを意識した制作に関する問題です。
DEIの中の公平性についての視点で留意すべきは、
どの視点での公平性を重視するかではないでしょうか。
ゲームではその、世界観が重要な役割を担っていますが、近年のゲームではポリコレの影響で
世界観を逸脱した登場人物が多数登場したことで、世界観を破壊したとなり批判の的となっています。
この現象は世界的に起こっており、ユーザー視点では世界観においての公平性が重視されていることが分かります。
しかし、制作側からすると、登場人物というポジションの数においての公平性に重点が置かれた結果、
社会や世界はそれをポジティブには受け取らなかったという結果です。
ユーザーや社会の目という部分では、日本も同様の動きがあり、
SNSを通じてのコメントによる意見や非難がより社会的影響力を持つようになったことは、
言うまでもありません。
公平性の視点の違い
ここで分かるのは、公平性がどの視点で見ているかで評価が変わってくる点です。
これまでの公平性については、企業価値を向上させるために会社内の組織や活動、
プロジェクトに対して評価がされてきました。
そのため、会社内での女性比率や人種への取扱い
プロジェクトやコンテンツでのジェンダー配慮や調整を行うことが良しとされてきました。
しかし、実際にプロジェクトやコンテンツにこれらの価値観を投入した場合、結果は大きく変わります。
コンテンツにおいての公平性は、世界観へのリスペクト、歴史的解釈の精度などへの公平性でした。
この点で言えば、プロジェクトが進行される中で、権力者による暴走や忖度を防止するための公平性が必要なのであって
男女比や人種比率などの分かり易い公平性をコンテンツに盛り込んでしまったことが問題の根本なのではないかと分析しています。
すると正しい公平性というのは、
権力者の暴走や政治的忖度が行われないようにするための人事や、
暴走が誘発しない仕組み作りを示す方が、新しい公平性と言えるのではないでしょうか。
ですが、これらの仕組みや考えをフレーム化するのは、容易ではありません。
何故なら、これらは仕事について上流から下流まで精通している必要があり、
最も問題なのは、これらを包括的に判断でき評価できる人間がいないことです。
また、評価を端的には表現できず、これらを仮に社会に公表したところで伝わらないものになると予想しています。
結局は、性別や人種、宗教といったカテゴリーではなく、
個々の能力や性格に基づくものになってしまうと予想されるからです。
またこういった権力者の暴走を防止する仕組み作りにはデメリットもあります。
一つは、プロジェクトの推進力が失われることです。
強力なリーダーシップは、部下や関係者からすれば、
パワハラや過度なプレッシャーとも受け取られかねません。
ここでのパワハラは暴力的な行動というよりも、
実現不可能にも思えるタスクや仕事のことです。
勤務時間中では達成出来ないようなタスクは、
プライベートや家庭、家族に犠牲を求めるでしょう。
受け手はこう思うでしょう。
公平ではない、会社は社会的責任を果たしていない。
ですが、現実は少し違います。
大企業の安定した職業のイメージといった神話が崩れて見えているように
会社もまた、強い外圧や競争に晒されています。
結果を出せなければ会社も生き残れません。
そんな中でホワイトなことばかりを言うのは簡単ではないのです。
だからプロジェクトには大抵、何度か試練が訪れます。
その試練を乗り越えるには、時に剛力が必要だったりします。
強引なリーダーシップがなければ乗り越えられない時があるんです。
公平性を重視した仕組み作りの中に権力者の暴走を抑止する仕組みが仮に出来た場合、
プロジェクトが座礁しかけた時にネガティブに働く可能性がおおい考えられます。
きれい事だけでは、プロジェクトは完遂できない。
一度仕組み化してしまうと、大失敗をするまで変えることができないので
この辺りの仕組み化においての線引きが、繊細で難しく、
承認を得ていくことの難易度も非常に高くなりそうだなと思いました。
よく考えてみれば、プロジェクトの完成度や精度を求めるのなら、
剛力が横行するプロジェクトは、コンテンツの公平性は高いものになるとも言えなくもなく、
矛盾が生まれます。
成功事例からCSRを考える
株式会社Yutoriの社長が最近注目されています。
若者を中心したアパレルブランドの会社を経営しており、企業の成長と合わせて、
若手社員の育成においても注目されている会社です。
この中での取り組みでは、社員に対するレビューは非常に厳しいものでも有名ですが
社員の満足度は高いというものでした。
これらはYoutubeなどを通じて発信されており、オープンな環境が見て取れます。
この点をCSRの観点で考えると、一つは透明性が考えられます。
Yutoriの働き方をみると、一見してストレスフルです。
CSRの観点から考えると、働き方としては真逆を進んでいるように感じます。
評価できる点は、これらのストレスフルな状況が見えている環境ではないでしょうか。
最初からプレッシャーのかかる職場であり、役割と責任は重いものだとイメージできれば
Yutoriで働くことを最初から考えない。ミスマッチを外すことができ、
CSRの観点で言えば、説明責任は果たしているとも言えます。
ですが、株式会社Yutoriの面をそのまま受け取るのは危険です。
まず株式会社Yutoriの特徴があり、再現性が高いかと言われるとNOです。
株式会社Yutoriでは自身のブランドが持てるというゴールが近いところにあるのが特徴です。
一般的なアパレルでは、一つ一つのブランドを大切にしており、一つのブランドを育てるために多くの人が関わります。
そのためブランドを任させる人間は、組織の中ではごく僅かで、非常に長いステップが待っています。
Yutoriにおいては、このプロセスはある程度、他社と比べて簡略化されていて、
入社すぐからでもゴールが見えやすい特徴があるため、セルフブラック労働であっても許容できることが推察されます。
また、人の出入りは激しいものと予想され他のアパレル以上に
GAFAM的な能力ともにモチベーションの高い人だけが残っている可能性が高いです。
この出入りの多さを自社が許容できるかが鍵にもなるでしょう。
一般的には、出て行く一方で入って来ない。こんなことが予想されます。
出入りのバランスをとるためには、若手のモチベーションの維持が出来るゴールと、
ゴールまでのちょうど良い距離が必要そうです。
セルフブラックはCSRの観点からも許される
今までのCSR的な視点からすると、盲点だったのではないでしょうか。
敢えてストレスフルな環境であっても、本人が許容できているかが重要なように感じます。
もう一つの点は、事前に告知されていることです。
情報発信の中で、ストレスが掛かる場所であることを明示しておく点が、
他社との大きな違いであり、隠さず告知されていれば配慮をされているとも言え、
CSR的とも言えます。
とは言え、どの業種においてもブラックなところが存在していることを考えると、
Yutoriの見せ方や演出が上手い言わざるを得ません。
次ぎの時代のCRRは、部署やプロジェクトごとに
成功事例から考えても、CSRを体現するには特性や工夫、時流なども関係していることが考えられます。
他の企業に当てはめたところで全てが上手くいくとは思えません。
また、モチベーションを維持させるためのゴール設定が魅力的で、わかりやすい必要もあります。
難易度が高く再現性は低く感じます。
ここで思ったのは、会社全体でCSRを考えるから破綻するのではないか。
採用の募集要項にあるように部署やプロジェクトごとCSRを定義すればよいのではないか。
というものです。
環境の格差は報酬や待遇などで差別化をし、定義してしまえばCSR的とも言えます。
開示されており、事前に把握できるものであれば公平的です。
細分化することで、問題の一部は解決できると感じています。
ですが、モチベーションや採用面での期待値をどのように上げていくかが解消されていません。
そこで必要になるのがCSR動画ではないではないかと感じています。
次ぎの時代のCSR動画
部署やプロジェクトごとにフォーカスした、働き方の動画を作ります。
やり甲斐や達成感を踏まえながらも、ポジションや役割に対する責任に関わる部分をオープンに見せることで
魅力を伝えることができるのではと感じています。
自分のブランドや責任あるポジションだけが、報酬やモチベーションではありません。
少ない労働が魅力になる場合もありますし、
コミュニケーションが最小限でいいような場所も魅力になるかもしれません。
一見、ネガティブや魅力にならないような要素も掘り出してみれば魅力に変えることも可能です。
こういった魅力が働くモチベーションとなるような演出がされた、
動画はこれからのCSR動画になるのではと感じています。