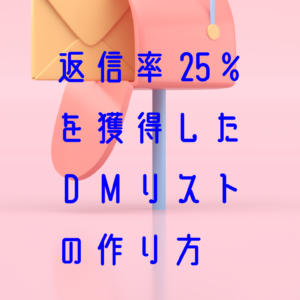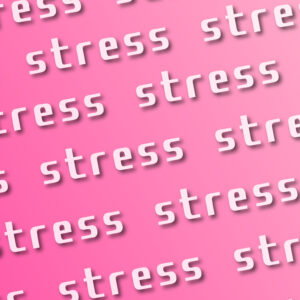はい、私です。
カメラを持ち、写真や動画を撮っていると、
解像度が気になってきてしまうもの。
今持っている機材よりも解像度が高いとなれば
ついその機材が気になってしまう。
そんな風になっていませんか。
はたまた、スマホでも何とかなる時代にカメラを持ち出してわざわざ撮る理由。
クライアントにどう説明したらいいか。
カメラオタクの独りよがりになっていないか。
今後の予想なども踏まえて考えていきたいと思います。
解像度って何だ
解像度は緻密さ、より多くのピクセル描写による高精細さではないでしょうか。
細かいピクセルによる表現により、微妙なディテールがはっきりすること。
細かいものの輪郭線がはっきりすることで精細さを感じられる。
こうったものを解像度と呼ぶのではないでしょうか。
解像度についての参考:解像度とピクセル数と用紙サイズの関係
あれ? 何故、こんなふわっとした表現なのか。
解像度はピクセル数だ。ドヤればいいじゃないか。
そう思っていた時期もありました。
なんか、ちょっと違う…………。
参考の資料も含め解像度は印刷やディスプレイ上の表示における解像度を表していることが多く
スマホやカメラの解像度は少し違うということが分かりました。
スマホの写真とミラーレスカメラの写真と比べたら違うよねということです。
スマホとカメラの解像度
スマホはもはやカメラなのでは?
と思いたくなるくらいに新製品が出る度にアップデートされています。
今は4Kは当たり前で8Kで撮影できてしまうものも登場し、ミラーレス不要論まで出てきてしまいそうな勢いです。
とは言え、ミラーレスカメラをお持ちの方ならスマホの写真はミラーレスに勝てないと思っているでしょうし、
私もその一人です。
カメラに搭載されているイメージセンサーの解像度を示す指標の一つである画素数ですが、
スマホもミラーレスも画素数はそれほど違いがないのが現状です。
画素数はピクセル数ととりあえず同じような考えていいと思いますが
画素数が多ければ、ピクセル数が多くなり、細かい描写が可能という気持ちで受け取ってください。
だからスマホもミラーレスも正直、
画素数ではどちらも同じレベルになってきているので判断がつきません。
では解像度は同じなのか?
と、問われると違いますよね。
ミラーレスの方が綺麗です。
画素数が同じレベルならば解像度も同じ感じになるはず。
しかし、そうはならない。
画素数が似たりよったりなのに、何故違うのか。
ちょっと調べてみました。
ピッチの違い
解像度は画素数、確かにこの相関関係は確実にあるでしょう。
小さなスマホにどうしてあれだけの画素数が出せるのか。
その違いについて、少し見えてきました。
画素数のピッチの違いです。
画素数は受光部、フォトダイオードの数を画素数と呼んでいると思いますが
そのピッチがミラーレスとスマホで違うようです。
参考:スマホのカメラ性能はどこをチェックすべきか?画素数だけではわからない比較ポイント
スマホのイメージセンサーなどはスマホのメーカーが開発しているわけではないので、
公式発表されているものは少ないと思いますがピッチは「2マイクロメートル」前後のようです。
ミラーレスカメラはどうなのか
https://hinden563.exblog.jp/30194989/#google_vignette
この記事を見ると6マイクロメートル前後になっています。
メーカーから公式発表はほとんどされないので、
センサーサイズと発表画素数から算出しているものになると思いますが
ピッチのサイズ幅が広い違いがあります。
この違いはなんなのかというと
https://kakakumag.com/camera/?id=19405
この記事の前段では、ピッチが広いことでフォトダイオードの面積が大きく確保できることで、
一つ一つの画素が大きくダイナミックレンジを広げることができる=高画質化ができるという表現をしています。
高画質に関して新しい言葉が登場してきました、ダイナミックレンジ。
ダイナミックレンジが広いことで白飛びしない高画質な写真が撮れると記事には書いています。
ダイナミックレンジの話は一度置いておいて画素数の話に戻りましょう。
現在の情報を整理すると、スマホとミラーレスとは画素数が同じでもピッチの違いで一つの画素のサイズが違う。
これにより、画質が変わるだ。と言えることが出来そうです。
しかし、スマホのサイズで実現できているのだから
ミラーレスは100メガピクセルや200メガピクセルにならないのでしょうか?
ノイズ×採算性
先程出てきたダイナミックレンジという言葉、
紹介した記事では、ダイナミックレンジが狭いことで白飛び部分が発生してしまい、綺麗な写真ではないと紹介されています。
誰が見ても古く感じる写真ではないでしょうか。
さて、α7R5などの高解像度ミラーレス機で白飛びした写真を撮影した場合、これを高解像度と呼べるのか?
呼べないですよね。今はスマホでも同様だと思います。白飛びしているものは高解像度と呼べない。
白飛びしているものは意図的でなければ、「ダサい」「古い」「失敗」したと、つい感じてしまうからです。
であるならば、ダイナミックレンジも一般的な解像度という概念においては、重要な要素になるのが分かります。
しかし、ここで大きな問題が出てきます。
解像感を高めるためには、多くの画素が必要なのですが、ダイナミックレンジを広げようとすると、ピッチを確保する必要が出てくる。
狭すぎるピッチの画素は、間に余裕がなく、光りが奥まで届かずにダイナミックレンジが落ちてしまいます。(仕組みが複雑なため抽象的な表現をしています)ということは、センサーのサイズが基本的には大きい方が画素一つのピッチ(面積)を確保でき有利になるわけですが…………。
広いセンサーを動かすためのコスト
大は小を兼ねるとよく言ったものですが、それは大飯ぐらいということでもあります。
センサーにとっての飯とは、電力です。
大きなセンサーには大きな電力が必要となります。
大きな電力をセンサーにかけると問題になるのがノイズです。
回路は水道管のようなものです。
水を流せば、色々なところで僅かに水が染み出します。
これがノイズとなります。
また回路は、画素を司るフォトダイオード一つ一つに繋がっているため、画素数を増やそうとすればするほど
回路も増え、ノイズが増える要因にもなってしまうのです。
カメラのセンサーは、ノイズに敏感に反応してしまい、
ノイズは、画質に直接影響を与えチラ付きやディティールの劣化に繋がります。
解像度を確保するためには色々なバランスをとる必要が出てくるということです。
ミラーレスカメラが100、200メガピクセルといった高解像度カメラが出て来ないのは
こういったダイナミックレンジを含む解像度を発揮するためだと推測できます。
採算性の問題もあるでしょう。
正直、解像度これ以上必要か?という状況にもなっています。
多くの人はスマホで画像を見ています。
高解像度でも小さな画面ではスマホのモニターや投稿先のプラットフォームの影響で解像度の圧縮が行われ
スマホでも十分な解像感は確保されてしまっています。
またディテールに対する人間の目の限界と言いますか、一般的な写真でも
よくよく見てみないと分からないくらいの違いしかなく、デジタルサイネージパネルに表示する広告や映画など
大画面で出さない限り、微細な部分に気付きにくいというのがあり
ある意味、一定以上の水準は確保してしまった。
と、言えるのではないでしょうか。
この状況で、解像度の高いカメラをどれくらいの人が欲しがっているのか。
想像に硬くありません。
100メガ、200メガのカメラを作ることは出来るのだと思いますが、それを何人が買ってくれるのか…………。
メーカーも商売ですので、売れないもののために開発は出来ないというのが心情でしょう。
スマホの綺麗な写真や動画どのように生まれてくるのか
話を改めて戻すと、ミラーレスはスマホに負けているのか?という点ですよね。
負けてません。スマホは写真や動画にバフをかけているだけです。
ふた昔前なら、解像度が高いだけで高画質だったのに、今は綺麗なものが高解像度
という一つの概念になってきています。
だからこそ、スマホのバフが通じるとも言えるのようになったのでしょうが………。
改めて、現代の解像度の条件を整理し直すと下記のようになるのではないでしょうか。
·白飛び、黒つぶれしていないこと
·鮮明であること
ダイナミックレンジは、白飛びや黒つぶれに影響しているのはよく分かります。
また、色鮮やかであることは、彩度などの発色、空の青さが残っているなどの部分です。
彩度はスマホもミラーレスも補正できるので変わりませんが、空の色味などは
ダイナミックレンジの影響を受けるので、違いが出るところ。
鮮明さでは、ピントやディテール、主題への光りの当たり方が影響するでしょう。
かつては画素数が鮮明さの大きな違いを生んでいましたが、今はそうではなくなってきています。
好きな人からすれば解像度は「解像度」という一つの指標で見るとができますが、
そうではない人からすれば感覚でしかない。
高画質な感じ。
高画質な感じとは、上記の三項目で、その中の鮮明さは
解像度をベースとしながらも、その他の要素も多分に含まれていて、鮮明さの一要素でしかないのです。
スマホの解像度はHDRとAI技術によって作られている
スマホの高解像度な感じはいったいどのように作られているのか
スマホ側の視点で考えてみたいと思います。
スマホは際ほどの話にもあったように、
ミラーレスとは対照的に小さい面積に小さい画素を沢山詰め込まれています。
ピクセルとしての解像度が高い反面、ピッチの狭さからくるノイズが解像度に大きな影響を及ぼしています。
解像度は高いが、ノイジーなためぼんやりとしていてはっきりしない。
またセンサーが小さいために、白飛びや黒つぶれしやすく、綺麗な写真や動画にはなりづらい課題があります。
そこでスマホの写真は、AIの技術を活用して綺麗な写真に見えるように調整しています。
その一つがノイズ除去です。ノイジーな部分をAIの技術で綺麗に整えることで解像感を高めています。
しかし、ノイズ除去は基本的に引き算です。
あるものから引いて整えるのが仕事。
ノイズ除去により解像度は落ちますし、
これを綺麗と言うかはそれぞれの立場や環境によって変わります。
大きな画面になってくればくるほど、
ノイズ除去はリスクが高まりますし粗が目立ちやすくなってきます。
続いてボケの追加、主体のリライティング
鮮明さには、背景のボケ具合も含まれます。
解像度には関係ありませんが背景がボケることで、
主体が引き立ち、主体が鮮明になることで綺麗に見える。
また、AIが人物の形を覚えたことで、
被写体にだけ後から明るくするような処理もできるようになりました。
背景が明るくて人物が目立たなくても、AI処理の力によって明るくでき
写真の本来の解像度を無視して、鮮明さを確保することが出来るようになったのです。
HDR処理による白飛びの回避
さきほど登場したダイナミックレンジですが、白飛びを解決するための工夫として
HDRという技術があります。
HDRとは人間の見えている見た目に近づけようという技術です。
人間の目は、非常に広いダイナミックレンジを持っています。
例えば夜。街灯のない場所でも月明かりでなんとなく場所が分かりますよね。
遠くの山の稜線と空の境界を見分けることが出来るし、
路側帯や側溝の溝をなんとなく視認できます。
また日中でも太陽を直視しない限り、その周りの空の色を感じることが出来るし
窓の外に映るビルを感じながらもオフィスの照明の明るさも感じることができる。
これがダイナミックレンジです。
センサーには、まだそのダイナミックレンジの広さはありません。
(実際には開発はされているようですが、宇宙開発向けだったり先端産業向けで一般人の手の届くものではありません)
現状のセンサーでダイナミックレンジの限界を超えようというのがHDRという技術になります。
シンプルに言えば、明るい所と、中間の2枚の写真を撮影し合成処理をしてしまうという技なのですが
ミラーレスの写真ではこのHDRの技法は基本的には使っていません。
スマホでは早くからHDRの技術が導入され、さらにAIの写真分析技術と組み合わせることで
白飛びのない綺麗な写真や動画を撮影することができるようになりました。
これらの技術によって、スマホでも高画質な写真や動画が撮影できるようになったのですが
スマホの写真や動画はあくまで後処理やAI頼りであることを忘れてはいけません。
そして、これらの機能を使ったとしても、元々の解像度を上回ることはできないということです。
なので、何故ミラーレスなのかと問われれば、
可能な限り最高の状態で画像をキャプチャーした方が良いという、
お客様を思っての配慮であることを説明すれば良いですし
加工はミラーレスでも出来る点を付け加えておくのが良いでしょう。
スマホでもOKなのだから値下げしてほしいと言われたら
本当にそれで良いのか? 問い直しましょう。
スマホの写真はスマホの画面よりも大きなもので使おうとする
画像が粗くなりやすく、紙やWEBであっても粗が目立ちます。
ノイズ除去を行えばノイズ除去特有ののっぺりっとした輪郭線や細かなディテールない画像になります。
もちろん、それだけだったら気にならないのかもしれませんが
自社のホームページ以外は、隣のページや他の記事、横並びで比較されます。
それは、幸せなことなのでしょうか?
お金をかけてわざわざブランドのバリューを落とすこともないでしょう。
というようなことをオブラートと配慮と優しさをもって
お伝えすれば良いのではと思います。
そんなことはさておき、解像度の話に戻りたいと思います。
今まではスマホとミラーレスの比較ばかりしてきましたが、
カメラは毎年のように発売され進化をし続けています。
新機種が投入されればその解像度がどうなのかが凄く気になってしまうのも
仕方ありません。
大金を投じているのだから、今のカメラより高画質であって欲しいというのは当然の摂理。
だからこそ、これからのカメラの動向について考えたいと思います。
解像度の奴隷
新しいカメラに触れ、その画質に触れた時、今までのものが全て陳腐化してしまう。
その体験を一度経験してしまうと、もう戻れません。
薬物中毒のように、次ぎの新作カメラの性能の噂やリーク情報が気になって仕方ない。
その噂を見聞きする度に一喜一憂する。
そうであるなら、あなたは解像度の奴隷です。
さてここで問題になってくるのはカメラの進化についてでしょう。
画素数については現在、各メーカーとも大きな進歩がなくなってきています。
画素数でプロモーションする合戦も減ってきました。
全体的な画質の進化はこれからも続くのでしょうか。
個人的な予想になりますが、これから先、期待出来るほどの進化はしないと予想しています。
理由はいくつかあります。
CPUの行き詰まりと同じく、ある種のセンサーの限界に近付いているのではないか
センサー面積が大きくなれば、大きな電力が必要となります。
大きな電力を流すとノイズを発生させる原因となり、画質を悪化させる要因となることです。
画素数を稼ぐために細かなピッチにしていくとなると、より細かなパーツが必要になり、パーツの耐久性
センサーの大型化に伴う熱の処理など考えることが山のように増えていってしまいます。
センサーの機能を十分に発揮し、高画質化をしていくためには、今までのようなペースでは開発するのが難しいのではないか。
CPUと同じようにムーアの法則から外れ、ある種の限界値に近付いていると、推察できます。
画素数による高画質化に、もう意味を見出せなくなってきているのではないか
スマホの登場やNetflixなどの動画配信媒体の登場により、大きなものを見なくなりました。
大きな街頭ポスターやデジタルサイネージがスマホの登場で見なくなり広告効果は以前ほどありません。
大画面で出す必要性が減ったことで高画質である必要もより減って来ている。
決して消えることはありませんが、それはごく僅かとなり、広告の主戦場はスマホやPCから流れるものになっています。
それらの画面で見るものであれば、ある意味、解像度だけで言えば現状スペックでも十分なのでしょう。
それよりも使い勝手やよりプロ目線での改良が求められているように感じます。
また、スマホのカメラも十分に進化したことで、
わざわざカメラを買う必要ある人も減ってしまったとも考えられます。
運動会や家族での旅行も思い出を撮るだけならスマホで十分です。
カメラは、プロユースか、より趣味でやりたい人のものになってしまったと言えます。
カメラも売れなければ開発費にお金を投じることができない現状を考えると、
台数を売れるスマホの方が進化目覚ましいという構図になってしまっているのでしょう。
AI処理によるアップスケーリングとノイズ除去
忘れてならないのが、AIの進化です。CanonのR5MK2の主な進化はAF周りの進化とAIの進化でした。
これらの状況から予想しても、画質に関しては、ノイズ成分の除去はAIに任せ、
ピクセルの隙間もAIの技術によって補間し高画質化を図っていくことが予想されます。
人間の目としても現状のセンサーでも十分高画質に見えている点であとは
補間をする程度でよいというのが、総合的な判断になってくるのではないでしょうか。
わざわざ巨額の開発費を投じて、微々たる結果しか出ないのであれば中々首を縦に振りづらい。
またユーザーの視点から考えても高画質化することで一枚のデータ量は増えHDDを圧迫し、
連写性能も上がらない、ダイナミックレンジも上げづらいとなれば
解像度に対してのトレードオフがあまりにも大きすぎる。
となれば、全体としては賛否両論。
コアユーザーの支持しか受けられないとなれば、
ある程度以上の解像度を確保した上でそれ以上の部分は
AIと協調しながら解像度を上げていくことの方が現実的なのではないか。
と、邪推してしまいます。
解像度の奴隷である喜び
ここまで色々と否定的なことばかりを並べてきましたが
解像度の高い一枚を見た時、これまでの全ては、ただの「言葉」でしかなくなってしまうのです。
繊細さ、緻密さに息を呑み、ただただその解像度の深さに酔いしれる。
それだけでいい。
自己満足です。
美しいに際限はありません。
ただ、ただ、よりよいものを生み出してくれたカメラメーカー各社に頭を垂れ、
次ぎの機種に胸を膨らませる幸福を噛み締めるのみです。