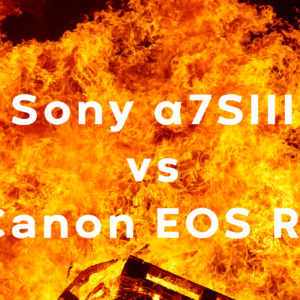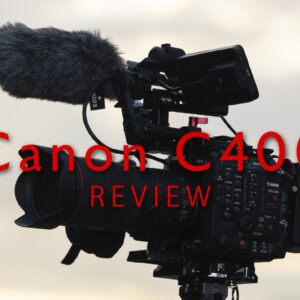YC Onion pineta proを半年近く使用しました。
最近、Youtubeで取り上げられまくっていた噂の一脚。
あまりにも持ち上げているので、本当に使える一脚なのか。
そう思い自分も購入してみました。
情報に踊らされているだけだったのか。
その答えを、貴方も見極めてください。
※ この記事にはプロモーションが含まれます。
YC Onion pineta proの性能
カーボンファイバーロッドを使用したワンタッチ式の一脚。
- チューブ径 39mm
- セクション数 3
- 最高高 1620mm
- 折り畳み長 780mm
- 耐荷重 10kg
- 重量 1780g
2段階の角度調整機能付きのペダルロック機構を持ち
一脚部分の固定、解除が可能。
スプリング式3/8、1/4インチネジの切り換えができ、
スチール用からビデオ雲台まで幅広く取り付けることが可能です。
特徴はなんと言っても、一脚の展開能力。
ハンドルを握る事で、ロッドのロックが解放されワンタッチで高さを調整できます。
この調整機能が目玉で一脚の常識を破壊し、イベント撮影などタイムリーな現場で活躍しそうです。

従来のロック式の問題点
従来の三脚、一脚は足の数、セクションごとにロック機構が設けられており
三脚では、それぞれ3本の足の高さをセクションごとに解除、固定をして設置する必要がありました。この方式はどうしてもセッティングまでに時間が掛かります。そして、やってみると痛感すると思いますが、微調整が難しく一人でカメラを据えた状態で調整するのが難儀します。
そのため、アシスタントに三脚のロック解除と固定をお願いすることで
セッティングのスピードを確保してきた背景がありました。
とは言っても、スーパーアシスタントでもない限り、先輩からのプレッシャーや疲労で、
経験不足などで上手く調整できない人もいます。
あとは時間的なプレッシャーでハーフボールが傾いたまま調整してしまいより、
三脚が歪になってしまうことも多々あり、意外と難しいのがこのロック方式です。
この方式は一脚も同様。さらに言えば、一脚はそもそも三脚を使ういとまが無い人やアシスタントを呼べないような現場や場所で使うことがほとんどであるため、このロックを自分でやる必要がありました。
さらに足が一本しかないので、カメラを置いてセッティングするのが非常に難しいのです。
カメラ位置を計算して、どの足を使うかを考えつつ、微調整しなければなりません。
先端にあるセクションのロックは、どうしてもカメラから目を離し、大きく屈む必要があるなど、安全面を考えるとカメラを一度地面に置いて、一脚をセッティングした後、カメラをセットするようなプロセスになりがちで、スピードと効率はどこへいったのか?
これなら三脚でいいんじゃないか。
これが一脚が流行らなかった理由なんだと思います。
期待していたスピード感が出ない、効率化されない。三脚と変わらない感。
ここが一脚最大の課題だったのではないでしょうか。

革新的なワンタッチ方式
pineta proが見せてくれた世界はその常識を破壊するものでした。
足下をもう見なくて済むのです。
カメラを一度地面に置く必要もありません。
カメラをセットした状態でも足の調整ができます。
求めていた一脚とはこういうものだよ。
これを体現してくれるのがワッタッチ式のロック開閉機構です。
ポール上端にハンドルが付いており、ハンドルを奥に握り混むことで、
ロックが解放されます。すると3つのカーボンチューブがするりと地面に落ち一脚がセットされます。
ハンドルの握りを緩めると各セクションのロックが掛かるようになり、
一脚が固定される仕組みです。
目線を外さないことで得られる快適性
スピード感が段違いです。
一脚だけのスピードというより、総合的な使い勝手としてスピードが増した感じです。
実際、イベント撮影のようなものでは、予想できる動きとできない動きがあります。
可能な限り予想できる中でセッティングチェンジの隙間を狙いますが、イレギュラーは当たり前のように起こります。
ですので、可能な限り主体から目線は外したくありません。
従来の一脚はどうしても軽さや高さを重視して、セクションスが多くなり、ロックがセクションの継ぎ目ごとにあり、
下を見ている時間が長くなりがちになるのと、セッティングまでのカメラをどうするのか? という問題に直面します。
結婚式場のような清掃も行き届いていて、大理石やコンクリートのような安定した場所からいいですが、
砂利や土のような場所だった場合、カメラを置くことを躊躇してしまいます。
そういった不安が頭を過らない。
矢木に電流は走らないのです。
考える数秒、判断を迷う数秒がないからこそ、スピード感を得られたように感じます。



秀逸なロック機構
pineta proは片手操作ができるロック機構になっています。
またハンドルのサイズも欧米人に合わせた大きいものではなく、日本人サイズになっているのも魅力的です。
ハンドルとポールまでの距離が絶妙で、ポールに指を掛けながらも手の平で押せるくらいの位置にグリップが位置しています。
お陰でポールを指先で支えながら手のひらでグリップを解除し、
一脚の伸縮が行えるので空いたもう一つの手はカメラをそのまま支えながら調整ができ、
ワンアクション減らすことができます。
ロックのバネ圧も軽い方で強い力は必要ありません。
カメラが載っている時は筋力よりも要領が重要といった感じでした。
ロック機構の詳しい仕組みは分かりませんが、カメラが載っている場合上から加重が掛かっているため、
どうしてもロック解除にも影響が出てしまう感触があります。
ですので、一瞬振り上げるようにカメラの加重をポールから逃がしつつ、
グリップを押し込みロックを解除することでスムーズな伸縮が可能になるという感触です。
個体差もあると思うので、この辺りは実際に試しながら
自分にあったやり方を探っていくのが良いでしょう。
足下の角度調整機構
斜面や不整地でも使えるように工夫されています。
足とポールとの間にスイベルベースが設けられており、ロックを解除することでポールの角度を調整できます。
角度はプラスマイナス18度。スペックだけでみると足りないと思うかもしれませんが、実用は問題ない角度です。
正直、20度も角度がついた斜面はかなり不安定な場所です。
すると現実的には、一脚の足を展開する使い方よりも、
ポールを突き刺してカメラを安定させるような使い方になるのではないしょうか。
足を展開しても角度が付きすぎて滑ってしまう感じがありますし、流動的にそのような場所に入るのはそもそもリスキー。自分の安全すら危ない場所なのではと思ってしまいます。
そういった場所なら遠間から予想しつつ最初から三脚を持っていく選択になるような気もします。
不整地であればこの18度で十分かなといった印象です。
とは言え、角度をつけた状態でロックをするのは実質できません。
ストンプ式のレバーでロックを解除することになりますが、ロックは直立の状態でしか機能せず、
それ以外の部分ではフルード状態です。硬さを調整できるノブがありますが、足下にあり現場で触るのは難しいかなと。
ある程度、自分の調整しやすい強さトルク感にしておいて必要に応じてロックを解除し、カメラを手で支えながらバランスとるのが一般的な使い方になるはずです。
ロックは硬めで、誤操作防止の観点からかレバー自体も小さく、
ロックを解除するのには足をしっかり中に入れる必要があるように感じました。
全ての角度でロックが効くようにしてほしいとも思いましが、機構的なことを考えると、
本体重量とトレードオフしたのではないでしょうか。
あまり重い一脚は使われないですし、妥協点といったところだと思います。
自分にあったセッティングが出てき慣れれば許容できる範囲だなと思いました。





2段階調整付きの足
一脚を支える足にも角度調整機能があります。足の開きを2段階調整でき、
収納時と伸ばしきった時とを入れると4段階とも言えるかもしれません。
足自体は、金属製で不安感はありません。
足は大きめ。ゴム足が付いていて、どんな場所でも使えます。
足のヒンジは少し緩めで足を広げる際に重さは感じませんでした。
ポール中央にもゴム足になっていて、足を畳んだ状態でも本体にダメージがいかないようになっています。
角度調整はエントリーからミドルクラスの三脚に付いているバネロック式で、
特定の角度でロックが掛かり反対方向に開かないようになっている仕組みです。
剛性は申し分ありませんが、ロック機構が緩いので、衝撃で足が開いたり動いたりします。
実際に使っていると、移動時に足に当たったりして、一脚の足が一つだけ違う角度になったりしました。
実際に使っていて感じたのは、この角度調整は不要だったと思います。
理由は、このロックが緩いために何らかの衝撃などで一つの足だけ、別の角度になっているということが
何度が発生して、それを直して使用するということがありました。
これが起こってしまうとワンタッチ式のメリットが大きく損なわれてしまい、
直すのに一手間、二手間かかり、時間をロスするのと目線が外れてしまう。
タイムリーな現場ではストレスになると感じました。
あまり角度を高くした形で使用することがないというのもあります。
一脚はそもそもその足だけでカメラを支えているので、角度を付けて足を狭めれば狭めるほど、
バランスを取るのが難しくなります。標準レンズに一眼だけというスタイルならまだいいかもしれませんが
中望遠クラス以上のレンズを付けた場合、不安定さが出て来るので使う機能ではなかったと感じました。
雲台について
Penta proには雲台が付いていますが、使用していません。
ムービーを基本としていますが、耐荷重の許容を超えているため最初から除外してしまいました。
袋から出した触り心地としては、ミラーレス一眼までの利用範囲だなと思います。
上下のパンアップ、ダウンには有効ですが、左右パンには使えない感じのもので、
最初に購入する分には有用かもしれませんが試行錯誤して購入を検討している方には向かないと思います。

ローアングルセッティング
この一脚のもう一つの魅力はローアングルセッティングが行えることです。
伸縮ポールを取り外してスイベルベースにマウントを直接取り付けることができます。
この機構はPenta pro独自の機構になっているので、他のメーカーのものを差し込むようなことはできません。
しかし、YC Onionのサイトに行くと、マウントアダプター単体を販売しているので、
雲台を切り換えたりするのは簡単です。
手軽にローアングルができるのは魅力的です。18度と制限はありますが、水平をとるのはそれほど難しくなく、
一脚を支えていた足なので、ローアングルにした時の安定感は抜群です。
フィックスのローアングルを数秒で実現できるのはかなり効率的ですし、
他のアクセサリーやカスタムが必要ないのも魅力。
荷物を増やさず機動力を維持しながら簡単にセッティングチェンジができるのはブライダルなどの現場で、
かなり便利なんじゃないかと思います。


デメリット
この製品にもまだまだ弱いところはあります。
折り畳み長の長さ
ワンタッチ式にしたことの最大のデメリットがここです。
折り畳み長が780mmは、やはり長い。
机の下辺りからのローアングル煽りのショットなどが作れません。
構造的にこれ以上短くできないので、水平位置か俯瞰位置から狙うようになってしまい、
アングルのバリエーションに制限を受けます。
足を外してローアングルから狙えばとも思いますが、
足を取ってしまうと、ベタベタのローアングルになってしまい使い所が限られるので、
その隙間が埋まらないのが弱点です。
また長いことで持ち運びには苦労すると思います。
リュック型のカメラバックに挿すと頭を大きく飛び抜けますし、
横に縛り付けても上下が飛び出すような感じ。
他の一脚の感覚でいると、失敗したと思うかもしれません。
重さ
すでに他の一脚を使ったことがある人なら重さが気になると思います。
ロック機構が搭載されているため重いです。
一番の重量になっているのは、足下のスイベルベースが比重が高い感触ですが、
カーボンチューブを期待していると後悔すると思います。
感覚としては、2世代前のアルミ一脚の感覚です。
軽さ重視することでスピード感を出してきたには向きません。
三脚の手間を省いて、効率的にフィックスのショットが欲しい。
こんな人に向けられているように感じました。
カメラ系Youtuberの感動は嘘ではない
この製品は非常に良いと思います。向き不向きありますが、個人的にはかなり使えるアイテムです。
だからこそあの誇張表現も嘘ではないのかなと。
気になる点としては、どうしても案件になってしまうとテスト期間が短く、
基本スペックの延長的なレビューしかできなず、長く使ってみて分かる事などが含められず表面的だったり
メーカーに迎合しているように見えてしまいがちです。
胡散臭く感じたり、信憑性が薄くなる部分もあるのですが……。
こういったものはある程度の期間、使ってみて善し悪しを判断できないですし、
写真や動画というものは撮影スタイルだったり、抱えている案件の性質の違いだったりと
視点の根拠となっているところが違うので、その点はどうしようもないのかなとも思います。
ですので、その点は、自分の経験とこれまで触ってきた機材の感触や評価を当てはめながら
想像で補いつつ言葉を咀嚼して腹に落としていく必要があるかと思います。
イベントカメラマンのための一脚
この一脚はスピードと効率を優先しているのでイベントカメラマンに最適なのではと感じます。
重さから判断してもプロ向けで、手持ちよりも安定したフィックス画をスピード感もって撮影する必要がある人向け。
ブライダルには少し大きく悪目立ちしてしまうような印象があるので、それよりも大きなフィールドに向いているように感じました。
自治体の行事やお祭りの記録撮影、フェスやイベントのメインステージ外をどんどん撮っていくような方に向いています。
企業の公式チャンネルなどのコンテンツ制作のような場合も有効に感じます。
ディレクターカメラマンスタイルの人にも向いています。
インサートショットや全景を撮る際に時間を掛けずにフィックスを撮る方法として便利だなと感じました。
総合評価、使い勝手
ネガティブな面もありますが一脚を使いたい人に理想的な一脚です。
三脚の煩わしさはありません。
足を一つ一つ展開する必要はなくカメラを固定するまでのスピード感は
一度はまると三脚から手が遠のきます。
もう全部一脚でいいんじゃない?
とまで思ってしまいます。
とはいえ、風に吹かれると揺れたりして画が乱れます。
カメラ重量と高さによもよりますが、風がなくてもたわみが発生して三脚の安定感を期待はしないでください。
街中の平らな場所であれば三脚のようなフィックスになることがありますが、
路面の状況や風、車の振動など影響は受けやすく構造的な弱点はあります。
手ブレ補正ありきで撮影したり、カットのバリエーションや時間を優先したい方に向いています。
本当に大切な決めのフィックスは三脚にした方が良いでしょう。
とは言え、編集する際のことを考えるとバリエーションのある方が結果的に良い物になるので、
一脚の方がアウトプット時のクオリティーを上げるのに役立つと感じました。