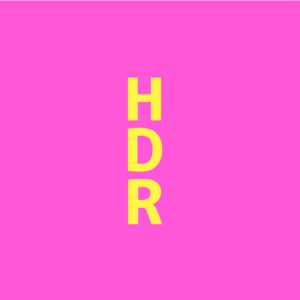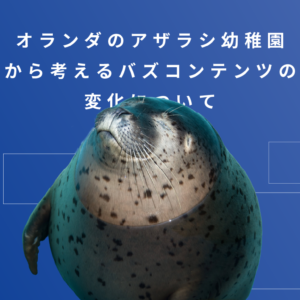野菜を栽培されている生産者向けに、どのようなプロモーション動画が良いののでしょうか。
そもそもどういったプロモーションがいいのか。
野菜を生産される方に合ったプロモーション動画のアイデアなどを紹介します。
と言っても、プロモーション動画なんて縁遠い。
そう感じている方も少なくないでしょう。
ですが、2023年の燃料高騰による肥料高騰の状況を考えると、
現状の販売価格では赤字になってしまう。
商品価値を高めるためにできること。
その一つに、商品のブランディングを行い、
生産物の価値を高めることなのだと思います。
またブランディングした商品を卸していく新しい販路の開拓。
商品のブランディングを行う点で、いくつか有利な点があります。
そのような点も含めて野菜のプロモーション動画がどのように役立つのか。
その作り方についても紹介し、何がプロモーションになるのかなどについても、
考えていきたいと思います。
プロモーションとは何だ?
さて、そもそもプロモーションとは、どんなものなのでしょうか。
Weblio辞書には、このような記載があります。
プロモーションとは、消費者の購買意欲をあおる活動という意味である。
日本語で宣伝や広報を表す、英語の promotion が語源である。
広辞苑では、「商品販売促進を行う宣伝」と書かれています。
商品は野菜ですので、野菜の販売促進を行う宣伝がプロモーションということになります。
では、どこに宣伝するのか。考えてみると、ここが難しそうな気がします。
ルーティーンでやっていると、納品先は同じですし、そこに宣伝を行うのは違うような気がする。
このように感じてしまうため、混乱が生まれてしまうのでは、ないでしょうか。
まず、何故「そこに宣伝をするのは違うような気がする」
という気持ちになるのか、紐解いてみましょう。
宣伝に対するモヤモヤの正体
宣伝は「押しつけである」テレビCMなどの制作をしている人や広告を作る人が常に意識している根本的な課題です。
この「押しつけ感」を与えてしまうことのデメリット。
そこがモヤモヤの正体です。
訪問販売の営業マンに不快感を覚えた経験は少なくないでしょう。
その時に感じた気持ちは、「ウザい」「うっとしい」「嫌な人」「悪い人」といった感覚を感じていたはずです。
その嫌な感覚を大切な取引先に与えてしまうのではないか。
そうなったら、もう取引してもらえない。
そう言った不安が宣伝に関するモヤモヤとしたものの正体です。
ですが、全ての人がそのように感じる訳ではありません。
野菜を欲しい人にとっては「渡りに船」となるわけです。
取引をしている人たちとは、すでに信頼関係があります。
ですので、わざわざ新たに宣伝する必要はないでしょう。
新しい人や新しい取引先を見付けるのが、
プロモーションというように考えるのがポイントです。
すでに取引している人や組織に宣伝をするイメージが間違いだったのです。
新しい取引先を考える
新しい取引先にも色々な形があります。
分かりやすい販売方法からプロモーションについて考えます。
イメージしやすいものがあると、プロモーションについて難しく感じていたものも
簡単に見えて来るはずです。
それではいってみましょう。
無人販売所
想像しやすい、新しい取引先ナンバーワンではありませんか?
無人販売所は取引先じゃないと思ってしまうかもしれませんが、違います。
今まで無人販売所をやっていなければ、それは新しい取引先です。
ここでの取引先は、無人販売所で野菜を手に取る一般の消費者です。
でも、もう少し深掘りができそうですね。
無人販売所を設置できる場所はどこになりますか?
多分、比較的畑や自宅から近い場所になるのではないでしょうか。
すると一般の消費者でも、知り合いや知人、地元の人の可能性が高くなります。
幹線道路の近くなどでは、観光で訪れた人も買いに立ち寄るかもしれませんが、
一般的には、知り合いや知人といった人を想定して考えるのが良いでしょう。
このような人たちは、多少の繋がりがあり、無理強いを強いるような営業をすると関係性が悪化しかねません。
ですが知り合いなので、お友達感覚や知り合いという安心感で野菜を買ってくれる可能性が高いです。
このほかにも、スーパーなどと比べて人の流れの違いなどありますが、細かくなりすぎてしまうため今回は割愛します。
道の駅などの直売所への出店
道の駅はイメージしやすい、新しい販売ルートの一つで思い浮かべやすいはずです。
道の駅も無人販売所も同じなのでは? と、思うかも知れません。
ここでは、「無人販売所」を自分達の土地に設置するタイプの独自の無人販売所と仮定義してお話しします。
そしてここの「道の駅などの直売所」は、自分達の土地以外の場所に出品し、野菜を販売することとして考えてください。
直売所の特徴
スーパーなどと違い、流通までのプロセスが省略されているため、利益を上げやすいのが特徴です。
そして、直売所はある程度の集客力があり、スーパーと同じように
野菜を買ってくれる期待値の高い人が集まっているのもポイントでしょう。
激しい競争とリスク
直売所は、他の生産者出品したいと考えていることが多く、人気です。
様々なライバルがおり、価格競争などに巻き込まれやすくなります。
そして、出品には当然出品費用が掛かります。売れなければ、赤字を出すことになるのが大きな違いです。
出品に掛かる費用などは、直売所それぞれで様々な形があります。
組合員になり組合費としての支払いや、売上金額の○○%を徴収されるケースなど様々です。
各直売所では独自のルールが設けられる、地元の生産者が優遇されているところもあります。
ですので、一ヶ所の直売所で勝手なイメージを持つのは避けましょう。
様々な所にアプローチし、その地域の全体像を掴むことが大切になります。
そしてもう一つ注意しなければならないのは、安全性です。
2014年には、道の駅で間違って毒キノコを販売し、食中毒事件が発生しています。
食中毒は、食品系においてもっとも危険なトラブルの一つです。
食中毒は、広範囲に多くの犠牲を出しやすく、過去には死亡事例も発生していることか
地域全体での社会的信用の失墜と賠償責任の追及など関係者を含め不幸にしてしまうことから
確実に避けなければなりません。
メリットである流通のプロセスが省略されているため、
野菜を検査する仕組みも簡略化されているため
出品者の責任は増大します。
直売所への出品は
このようなリスクがあることについても承知しておく必要があるでしょう。
清潔な社会の弊害
直売所での出品リスクとしてもう一つ考えれるのは、生産者と消費者の意識の違いです。
注意しなければならないのは虫などの小さな生き物の混入です。
生産者からすれば、それは調理前に台所で落として……。
くらいの感覚かもしれません。
しかし、都心部に住んでいる人は洗浄され虫一ついない野菜に触れていることが多く
観光地などに訪れる人の場合、都心部から訪れている場合も多く、
野菜への意識に違いが生まれている可能性が高いです。
その場合、小さな虫などの付着をSNSなどに投稿し、
ネガティブな拡散をされてしまうと、大きなトラブルにならないとも言えない
時代になりました。発信力のある都会の人の影響力に対しても
直売所で販売する場合は注意を払う必要があるでしょう。
コロナ明けで挽回できるか、観光系直売所
農林水産省のコロナ過の直売所の売上に関しての調査報告があります。
出典の中ので調査資料の中では、一番新しく参考になるのではないでしょうか。
出典:コロナ禍の農産物直売所の実態に関するアンケート調査報告
この調査報告では、観光地や中山間地域の売上が減少しており、
公社や第三セクター型の直売所が売上の減少に繋がっている報告になっています。
総合して考えると、道の駅や観光地にある直売所の売上は減少していると見てよいでしょう。
2023年6月現在、インバウンドの回復を見てみると、観光地での消費は期待できる可能性は高いと感じています。
出典:農林水産物直売所・実態調査報告
出典:全国農林水産物直売所・実態調査から見える直売所の今と野菜販売
スーパー、八百屋との契約取引
スーパーや八百屋への契約取引をすでにされている生産者も、少なくないと思います。
一般的には、一般消費者までの距離が近ければ近いほど、生産物一つの単価を高い形で取引することができるでしょう。
このような契約先を複数持つことが経営の安定につながり、社会的な揺さぶりにも強くなります。
とはいえ、それは一般論であり、鵜呑みにしてはいけません。
それぞれの契約内容がどのようなものになっているかによって変わります。
相手は、ビジネスマンです。当然、ある程度自分達にメリットがあるような形での契約を持ちかけてくるでしょう。
ですが、全員が悪人というわけでもありません。
メリットを感じて貰えなければ、契約を完了することは出来ないことを彼らも分かっています。
契約に強くなる
契約文章難しいですよね。
こんなものを改めて理解しようとするなんて、
なんて苦しい思いをしなければならないんだ……。
そんな気持ちでは、ないでしょうか。
分かります。
法律的な文法は、見慣れない漢字やルール、数字、計算方法などが記載されていて、
そもそも相手に理解させない仕組みになっているように感じます。
ですが、多くの生産者が同じことを思っているはずです。
あなただけでは、ありません。
だからこそ、ある意味で契約に強くなることで、簡単に他の生産者よりも優位に立つことができる
とも考えられませんか?
大きな投資を必要としないというのも、経済的にメリットが大きいです。
規模感や知名度のあるスーパーや八百屋と契約を進めて行くのは、この辺りの慣れは必須になってくるでしょう。
契約内容を紐解くヒント
難しい契約の文章を簡単に理解するためには、ブロックに分けて考えることをオススメします。
文章の内容には3つのブロックがあるように考えてみると、簡単に見えて来るかもしれません。
契約に関する文章の3つのブロック
・法的な部分
・取引に関する部分
・相手の提案する独自のルールの部分
多分ですが契約の文書はこれらが入り交じって書かれているはずです。
そして一番簡単なところは、「取引に関する部分」なのではないでしょうか?
この部分は、反射的に電卓を弾けるくらいよく知っている知識だと思います。
契約文章も知っている部分から内容を紐解いてみると少し文章が分かってくるはずです。
次ぎに理解しやすいのは、「相手の提案する独自のルールの部分」そして、全てを難解にさせている法的な部分です。
独自のルールは理解しやすいものから、複雑怪奇なものまで様々になると思いますので、経験と慣れが必要になってくるかもしれません。
すぐに契約しない
契約に関しては投げ出さず、解読していく必要があります。
そのため、すぐに契約するのは避けましょう。
「よく分からないけど、サインする」愚の骨頂です。
「よく分からないけど、書類だけ受け取る」ようにしましょう。
対峙している人が法律に詳しいわけではありません。
相手は、個人ではなく企業です。
細かいルールを決めている人はそこにはいません。
相手から見えない時間を作ることは、心理戦としても有効です。
そして契約内容を詳しく見る時間や相談する余裕を作ることにも繋がります。
若者を頼る
契約に関しては、若者に頼るのも一つの方法です。
若い生産者であれば、この辺りの知識や人脈を持っている人も少なくないでしょう。
全ての生産者がという訳ではないですが、ちょっとイケイケな感じの人であれば具体的に詳しい訳ではなくとも
ヒントが得られる情報は持っていることでしょう。
新しい交流が生まれる可能性も、あるかもしれません。
次ぎは新しい契約先を増やすことのメリットを考えてみましょう。
参考:農家との直接契約、探す方法やメリット・デメリットは?卸売業者との比較も
参考:野菜の契約取引の実態に関する調査結果について~第2報 実需者編~
情報の入口が増えることの強さ
情報は、加工されていることを忘れてはいけません。
何故情報は加工されるのか? 情報も料理と一緒です。
野菜をそのまま食べるよりも、調理して食べる方が美味しいように、
情報も業種ごとに関連した情報を加えたり、削ったり、推測を加えることで
届けたい人の意識に届く情報になるからです。
情報の加工は、同じ取引先からは同じようなテイストになります。
和食や中華というジャンルがありますよね?
情報も同じです。
同じ取引先からは、似たような加工がされた情報になりがちです。
すると情報が一辺倒になり、間違った情報や怪しい情報に気付きづらいのです。
新しい取引先を増やすことは、情報の角度を増やすことにも繋がります。
変化の激しい今を生き抜くには、複数の角度から情報を仕入れ、
本筋を見極めていくのが大切です。
野菜をブランディングしていくために
今よりも利益をあげていくためには野菜をブランディング化し
価値を高めていく必要があります。
そのための手段は様々あることはご存じかもしれません。
ブランディングの方法には規模感があります。
大々的に行うのか、小さくコツコツ進めていくのかこの二つです。
大々的に行うブランディング
ベンチャー企業など農業ベンチャーなどがマーケティングを含め
複合的な戦略を通して行うブランディングです。
このようなブランディング戦略を行う場合は複数の媒体に同時に
プロモーションをかけていきます。
紙媒体からテレビや広告含め同時期に多重のプロモーションをかけることで
一気に注目を起こしていく戦略です。
短期に集中的にプロモーションすることで初速を付け、
ある程度の認知度を獲得したのち、その認知度が低下しないような戦略をとります。
このようなブランディングを行う際にも動画は用いられます。
動画は主体的に使うものと、受け手として取材を受けるパターンの2つがあります。
大々的にプロモーションを行う際は、
主に受け手として取材され、メディアから発信されることが主な目標になります。
大々的にプロモーションできる条件
まず、事業そのものに革新性や独自性があるかが問われます。
大々的にプロモーションには必ず取材を受けるなど、
発信するだけではなく取り上げてもらうことが前提のプロモーション戦略になります。
そのため、取材をしたくなる材料があるかが問われます。
もし取材をしたくなる材料が乏しい場合は、効果的な組み込みが難しく
全体の戦略を補うため、プロモーション費用が増大します。
それでは取材に向いている材料のアイデアを紹介します
・革新的な要素があるか
・新しい品種
・新しい生産の仕組み
・研究要素が含まれている
・独自性があるか
・働き方として一般的ではない方法を採用している
・珍しい品種を生産している
・味の違いがあるか
・取り組みに魅力があるか
・文化的な価値がある(古代の生産方法などを採用しているなど)
・卸先に魅力がある
・評価されている信念がある
・時代に合っているか
・SDGsなどの取り組みの具体的な評価がある
・パートタイム労働など働き方への配慮がある
・少子化などの取り組みがある
・耕作放棄地など社会課題への取り組みがなされている
上記の内容が具体的になっていれば、
それらを題材に取材を受ける可能性は高くなります。
大々的にプロモーションすることを前提とするならば上記の要素の中でも
革新性や独自性を求められます。キー局などの取材では
これらの革新性がニュースとして扱いやすいからです。
雑誌などの紙面媒体も専門誌を除けば
「ライフスタイル」や「社会課題」への取り組みが記事になりやすく
これらと結びつけてプロモーションをしていくのが効果的になります。
マーケティングチームは野菜を様々な観点から評価し
生産プロセス含めプロモーションを考えていきます。
これらはある程度、事業の先行きが見え始めた時から計画し
プロモーションのタイミングを検討します。
そしてこのような大規模なプロモーション活動には
それなりの資金が必要になります。
複数からの取材に合わせて同時に広告を打つのが
短期でのプロモーションにおける戦略だからです。
大々的にプロモーションする上でも野菜のプロモーション動画は必要です。
それでは必要な動画を紹介したいと思います。
野菜が出来るまでの動画素材
野菜のプロモーション動画の位置づけとしては裏方ですが、テレビ番組などの取材を多く受けたい場合には有効です。
理由は、テレビ番組などの番組制作は時間がありません。
密着で野菜が種から収穫までを追うことはありません。
ですが、事業の革新性や特徴を紹介する上では野菜ができるまでの
プロセスが必要な場合がほとんどです。
テレビ番組を制作している側からすると
紹介したい内容(ナレーションや文章)に合う動画がない場合
紹介できないといったジレンマが発生し
様々な動画が揃っている紹介しやすい事業者になってしまいます。
野菜ができるまでの動画素材を持っておくことは
取材を受けやすくプロモーション活動を円滑に進めることに役立ちます。
商品のプロモーション動画
実際に販売する野菜のプロモーション動画です。
プロモーション動画の狙いは自社でコントロールできるPR動画を持つことで
クロージングに繋げやすくするためです。
取材は認知度拡大に役立ちますが、取材された動画を扱うことはできません。
版権は番組の放送局が持っており、扱いには制限があります。
一度認知度が拡大すると、商品の詳細を求めて検索されるのが一般的です。
そこで自社で使える動画を持つことで販売などに役立たせることができます。
これらはHPでも代用できますが、現在であればWEB、動画ともに準備するのが
検索に引っかかりやすくプロモーションの効果を飛躍的に高められます。
小さくコツコツ進める場合
大々的にプロモーションには様々な人や資金が必要になります。
プロモーションを行っても失敗する可能性が高いのも事実です。
野菜は気候や災害などの影響を受けやすく、プロモーションが成功しても
実際の収穫が上手く行かないなどコントロールできない面が多く
比較的、長期になるため大々的なプロモーションは
製品などもリスクが高いデメリットがあります。
コツコツと反応を確かめるのも、野菜のプロモーションでは有効は戦略です。
小さくコツコツと進める場合はより長期間で動画を使ってことを考えます。
期間は3~5年を使うペースでじっくりと考えていく必要があります。
1年で収穫のサイクルが2度、3度ある場合は3年程度で考えるのもよいですが
収穫サイクルが長いものは長期の戦略を見る必要があります。
コツコツ小さくプロモーションする方法
小さくコツコツプロモーションするためのブランディング戦略は
大々的にプロモーションとの大きな違いは
価格的な付加価値を最初に求めないことです。
小さくコツコツ進める場合は、独自の販路を拡大に徹します。
理由は独自の販路先は野菜の魅力を理解している人の確率が上がるためです。
魅力を理解してもらえている販路では、百貨店のバイヤーなどが立ち寄る可能性も高いなど
広がっていく可能性が高く、地道な露出、拡大がチャンスを広げていくからです。
ですが、このようなチャンスは運の確率が高くあまりそのような
未来を期待し過ぎないでください。
そのために野菜のプロモーション動画などを準備し、広げた販路でも
目立つようにするのがポイントです。
興味と納得を作るプロモーション動画
野菜のプロモーション動画を作る目的な購入してもらうお客様
一人一人に向き合うために使います。
お客様の現在の納得感は、商品を調べた時に出てくる情報の数とイメージです。
野菜一つにWEBサイトがあり、その紹介が生産者と友に紹介されていることは
まだ他の生産者の多くはやっていないため、希少性が高くこだわりを感じます。
お店のポップから商品を検索し、紹介が存在していることが安心感に繋がっています。
野菜のプロモーション動画では、作り手の想いが優先されます。
野菜を作るための技術的な違いやこだわりは、その野菜を作っている同業者にしか伝わらないのがほとんどです。
一般の方には、「そのこだわりがすごい」程度にしか伝わって来ないのが実情です。
ですから、野菜のプロモーション動画では技術的な割合は少なくし、
想いや経緯をベースに話しストーリーの中に技術を盛り込むのが野菜のプロモーション動画ではポイントになります。
それでは実際のストーリーの作り方の参考をもとにポイントを紹介します。
野菜作りのストーリーライン
生産者の想いはストーリーラインがあるとより伝わります。
一般的なストーリーラインをベースにポイントを紹介したいと思います。
1 こだわり
2 過去
3 野菜作りのきっかけ
4 失敗
5 成長
6 実現
こだわり
こだわりは、今作っている野菜のこだわりです。
味や色艶、質感、収穫のタイミングなど作られている
野菜のこだわりを話してもらいます。
販売店で紹介されているポップの内容ぐらいで問題ありません。
どこがこの野菜のすごい所なのかが分かるような紹介をします。
過去
ここから生産者の生い立ちを紹介します。
生い立ちは、野菜作りに関係ないように感じますが、人は持っている
バックボーンで印象が変わります。
そのため、いっけん必要ないように感じる過去の話も
野菜作りでは役立つ可能性があります。
そしてその過去から野菜作りに携わるきっかけについて
話しを繋げていきます。
野菜作りのきっかけ
物語の起承転結で言えば、「承」の部分です。
野菜作りの本題に入っていきますが、好きで携わる人もいれば
嫌々携わることになった人もいるでしょう。ここはネガティブなままでも問題ありません。
理由と状況が紹介できれば問題ないでしょう。
可能ならその時の畑の状態やその野菜の社会的な評価についても
紹介できると魅力が増すかもしれません。
失敗
失敗はストーリーラインを作る上で最も重要な要素です。
失敗談のない物語は面白くありません。
失敗談であれば誰しも一つや二つは持っているのではないでしょうか。
野菜作りに関わる内容が理想的ですが、必ずしも直接関係している必要はありません。
家族のことや私情でも大丈夫です。
大切なのは、最終的にその内容が野菜作りに関連するように
繋がることが大切です。
もし失敗がない場合はピンチや危機でも問題ありません。
野菜作りは天候や気候の影響、社会情勢の影響を強く受けます。
それらのテーマでピンチに陥ったことが、失敗の代わりになります。
成長
成長は失敗を受け、何を変えたか、変わったかを表現します。
失敗を受けどのように変わったかがポイントになります。
この取り組みによって、
達成される成果=今の野菜
といった流れにするようにしましょう。
技術的なこだわりがある場合については
ここで紹介するようにしましょう。
実現
失敗を乗り越え,成長したことにより最終的に今の野菜が出来てる流れができあがります。
ここでは、最初の「1のこだわり」に近い内容になるかもしれません。
改めて、どんな思いで今も野菜を生産しているのか話すようにしましょう。
このような流れで動画を作ることで、思いを感じる
野菜のプロモーション動画の流れを作ることができます。
しかし、あくまで一例であり、実際に作るとなるとストーリーラインも変化し
事実をベースに応用的に流れを作る必要があります。
そのため難易度が高く感じるので、このような部分は得意な人と
作っていくのがよいでしょう。
動画の使い方
動画は検索されやすいようにする必要があります。
そのため、ポップなどには動画が視聴できるように
QRコード化するなど工夫が必要になります。
タブレットなどが設置できるのであれば動画を
販売店で再生できるようにするのもプロモーション動画の活かし方です。
今はFacebookなどもHPのように使う方がいるので、Facebookへの動画投稿や
Googlemapから検索できるようにし、動画が視聴できるようにしたりするなど
導線を確保するようにしましょう。
WEBサイトを作る余裕があればWEBサイトを開設するのは
今後も違う野菜の販売や今生産している野菜を加工したものを販売していくなど
展開しやすさがあるのでWEBサイトと合わせてプロモーション動画を使っていくのが
長期で考えるとメリットがあります。
まとめ
まず動画を作る前に大規模なプロモーションを行うか
小規模で行うかで戦略を決めることが大切だと感じます。
それぞれで動画の使い方や使われ方、タイミングが変わります。
野菜のプロモーション動画それぞれの戦略のスタイルで作り分けを
行うのがポイントになります。