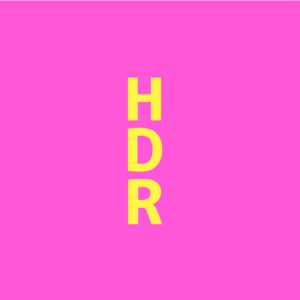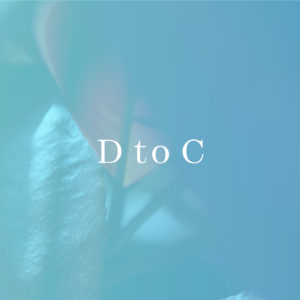BtoC向けの工場見学動画の作り方を紹介します。
社内で内製化することも可能ですが、内容によっては外注することを検討した方が良いでしょう。
その判断基準も合わせて紹介します。
工場見学の需要の高まり
工場見学が今注目を集めています。
それは工場見学が日本独自のものだからです。
外国人、インバウンド向けの観光需要が増加しています。
海外では工場を見学できるところがほとんどありません。
日本は、世界の中でも特殊で工場を一般人向けに公開していること自体が特別で、
海外の人からすれば魅力的な場所となっています。
インバウンドが観光地だけのものではなく、
地域や立地に囚われない新しい魅力の開拓に繋がるのではないでしょうか。
また海外に自社の製品の魅力をPRすることに繋がり、
販路開拓のきっかけを作ることにも繋がるかもしれません。
BtoC向けの工場見学の仕組み
すでに工場見学を実施されているところは飛ばしてください。
工場見学動画の話をする前に工場見学の仕組みについて紹介する必要があるでしょう。
理由は、工場見学の流れを把握することで工場見学動画の意味や使い所が見えてくるからです。
工場見学は、基本的に3つに分かれています。
1 自由見学方式
見学できる範囲やコースを作り、自由に見学できる方式です。
ジブリ美術館や東京タワーといった施設が似たような構造です。
出入口を設け、中を自由に観光できる方式です。
メリットは、一般的な工場見学よりも一人当たりの滞在時間を長くすることができる点です。
また、体験ブースでの一人当たりの体験時間を長くしやすいのと、体験ブースの集中混雑を緩和しやすくなります。
立ち入り禁止区域が物理的に遮断されていれば、管理に掛かるコストを少なくすることができます。
デメリットは、イベントや仕掛け、アトラクション的が少ない場合、面白みにかけネガティブな評価を受けやすいことや、
工場として稼働させている場合、無断侵入などの悪意ある行為のリスクは高まります。
また工場見学という特性上、一般的に通路は狭く、
生産ラインの流れを見せるには相性が悪いと言えます。

2 流れるプール方式


見学コースを指定し、コース順路はあるものの、見学のスピードは個人に任せる方式です。
富岡製糸場や大谷採掘場跡など、古くからある工場や史跡などであるので、イメージしやすいのではないでしょうか。
メリットは、順路を指定することで、
人の流れをある程度コントロールできるのが魅力で大人数のツアーなどにも対応しやすい方式です。
また、基本的には一通で順路を設けることで正しい生産プロセス順に見せることで誤解を与えづらいのも特徴です。
人のコントロールをしやすく、管理面でコストを調整しやすいとも言えます。
デメリットは、流されるままになってしまい、魅力を伝え切れないことが多いこと。
旧来の工場見学の方式のため、この流れに慣れてしまっている人にとっては、
反射的に飛ばしながら見てしまいがちです。
そこへ行ったことが記念になってしまいやすく記憶に残らない、といったことがおこりやすいでしょう。
また小さい子にとっては、縛られていると感じやすく、ウケが悪くなりがち。
解決方法としては、ルート上にいくつか見せ場や体験ブースを用意することです。
五感を刺激する場所を用意するだけで、子ども達の満足度を高めることができます。
また、音や煙、臭いといったものも有効です。
工場独特の熱や動く機械の音を生で感じさせてあげるのも、刺激的で満足度高め。
年齢関係なく普段、見ることのできない要素を盛り込んであげると喜ばれます。
しかし、事故や怪我、安全面でのリスクが高くなることについては注意や対策が必要となります。
大きな工場では工場見学用にデモレーンや、デモの体験を用意しているところもあります。
食品系の工場ではエアシャワーのデモを見学通路に用意し、疑似体験してもらえるような試みなどをしています。
3 ジャングルクルーズ方式
ガイドと一緒にグループまたは個人が見学コースを回る方式です。
工場見学を始めるにあたりイニシャルコストを低くでき、大規模にやらない場合などに有効です。
また、来場者の温度感に合わせることができ、内容も現場で調整しやすいのも特徴です。
メリット、ガイドがいることで、来場者の満足度を高めることができます。
工場見学では説明が命と言っても過言ではありません。
ディズニーランドやUSJと違い、行くだけで満足ということにはならないでしょう。
良かったと感じてもらうには、普段見られない世界を見せることと、そこでしか得られない知識です。
話を聞いてちょっと博識になれたなと思ってもらえるような説明やガイドが必要となります。
その他には、ガイドが来場者を管理することで、工場見学のための管理を最小限にできます。
デメリットは、ガイドの負担が大きく大人数をさばくことが出来ません。
また、ガイドの質に大きく依存し、満足度の差が大きくなりがちです。
ミニマムで始めやすくBtoB向けの工場見学の延長で考えてしまいがちで、
内容や案内のやり方によっては重大事故を誘発しやすい危険性があります。
一般人は業界の常識も暗黙のルールも知りません。
観光気分で神様状態になっている人もいます。
勝手に触ったり、進入禁止区域を踏み越えたりと、
管理するのは非常にストレスが掛かり、
担当者が悲鳴を上げている可能性があることを忘れてはいけません。
安全管理はしっかりと、工場全体で設計を行い、
工場見学のルートや内容を決定していくプロセスが必要となります。


工場見学動画とは
工場見学動画は、これらの工場見学をサポートするためにある動画のことを言います。
しかし、VRの登場などで工場見学動画の解釈が拡大し一概に工場見学動画と言っても様々なバリエーションがあります。
今回は、そのバリエーションを紹介していきます。
1 生産ライン紹介動画
工場見学動画というとこれが最も多いパターンの動画です。
工場見学動画と言っても、WEB上で視聴するために
作られたような動画で、工場が担っている仕事を
始めから終わりまで紹介するものになります。
メリット
この動画の良いところは、WEBでも使えるという点です。
工場見学行けない人のためにも使え、学習やPR的にもなります。
デメリット
工場見学の現場では使えません。
まず使い所が少なく、工場現場では最適化されていない点です。
はじめに動画が長すぎるために、どこで動画を流すべきか思案するはずです。
多分、事前に見せた方が良いと言う意見にまとまりやすく、
工場見学の始まりが動画となり、テンションを下げがちです。
はじめに動画が長すぎるために、どこで動画を流すべきか思案するはずです。
多分、事前に見せた方が良いと言う意見にまとまりやすく、
工場見学の始まりが動画となり、テンションを下がりがちです。
教習所の学科をさせられているような気分になってしまうのではないでしょうか。
せっかく目の前に工場があるのに、その魅力を活かせないパターンになりがちです。
とは言え、動画を分割したり、最適化することで全てを無駄にすることは無くなります。
動画はセクションごとに分割し、
動画を制作する段階で、使い所を説明し、
各セクションやブロックごとに動画内の説明が完結するような工夫をすると現場でも使える動画になります。



2 キャラクターによる仕組み紹介動画
工場が一般消費者向けの商品などを製造している場合によく使われています。
デフォルメされたキャラクターが低学年の子ども達向けに内容をシンプルにまとめ紹介しているパターンの動画です。
メリット
子ども達向けにフォーカスしており、
ターゲットが絞られた内容であるため、非常に内容がまとまっていることが多いです。
キャラクターという要素を除けば、大人でも学びの入口として有効で、
取捨選択が出来ているため大事なこところにフォーカスされていることが多いです。
また、動画の締めは社内的な意義や価値に触れていることが多く、自分達の仕事の意味を再認識するのに役立ちます。
子どもの集中力に合わせているため比較的、短尺でまとめることが多く、工場見学の現場でも使いやすいのがメリットです。
デメリット
大人が動画を見た瞬間に、自分がみるべきものでないと無視しがちです。
また、内容が子ども達の年齢とかなり低く見積もってしまいがちで、内容が薄くなっているものや、
仕組み全体の上澄みを浚ってしまいがちで説明内容が同業他社と同じになりやすいです。
自社や現場の工場の特性を紹介するものになっていないのも動画を活用仕切れない原因に
なっているのではないでしょうか。
3 VR工場見学動画
WEB上で工場を見学できるというものです。
VRといってもパターンがあり、本格的なものは、3D空間に工場を作り疑似的に動かすことが出来ますが、
簡易的なものはGoogleストリートビューのようなものと動画を組み合わせたものが多いです。

メリット
WEB上で使うことが前提のため、現場以外ので展開をしやすいのが特徴です。
一般向けのイベント出展のアクティビティなどで使いやすく、
システムがWEB上にあるため運用にコストも少なくて済みます。
また採用向けなど、自社を知ってもらうきっかけを作るなど、活用の幅は広めです。
デメリット
WEB上で利用することが前提のため、現場での工場見学に使える瞬間が最も少ないと言えます。
工場が雨など天候の影響を受けやすい場合の代替案としての予備的な使い方や、
ちょっとしたアクティビティとして活用の場があると思いますが、
目の前に工場があるのにVRをわざわざ使うのは、相当な理由が必要になるでしょう。
また、VR系の動画は他の動画制作よりも費用が大きくなりやすい特徴もあります。
4 説明看板方式
科学博物館など展示物の横に説明として設ける動画をイメージしてください。
目の前の内容を補足するのに使われることが多い動画になります。
動物園でも導入されていますよね。
夜行性の動物や警戒心の強い動物などは、奥に隠れていることが多く、
ケージ越しに見られない時のために用意されたものだったりします。

メリット
工場見学時と最も相性が良く、現場のフォローとして役立てることができます。
仕組みを紹介する説明として使いやすく、分かりづらい部分をアニメーションなどで、
補うことで満足感や学習効果が期待できます。
また安全上の制限で遠くから見られない場合や、
蓋などで中が見られない場合でもフォローとして役立てることができます。
生産ラインが稼働していない場合ような状況に活用できます。
ガイドがいる場合でも息抜きする時間を作ることができ、
状況の整理やグループ全体の温度感など掴み直す時間に充てることもできるでしょう。
デメリット
現場に相性が言い分、WEBなどとは相性が悪いです。
あまりにも分割されてすぎている点や、動画だけで見ると説明不足になりがちで使い勝手が悪いです。
見学ポイントごとに、説明動画があることでガイドが不要となりがちですが、
動画があるだけでは置物になりがちで生かし切れません。
DXや省人化を考えて検討している場合は、工場見学自体の魅力を損なうリスクがあります。
このような動画は、ガイドと組み合わせることで最大の満足度を生み出すものになるでしょう。
4つの動画のパターンを紹介しましたが、ミニマムで始めやすく、
実行有効性から考えても4の説明看板方式ではないでしょうか。
ですので、今回は説明看板方式の動画の作り方について紹介します。
工場見学動画の作り方のポイント
ポイントは、内容を一つに絞ることです。
説明看板方式の大きな特徴として、動画単体として分かりづらいのが特徴です。
一般的な動画であれば、導入があり、本題へと入っていきます。
しかし、説明看板方式では導入は入れません。
何故なら、動画を見る人は現場を見ているためわざわざ説明を入れる必要がないからです。
目の前に設備があるのに、動画でわざわざ説明されたらうざったく感じられ、テンションが下がってしまいます。
そのためにここの見学ポイントでどんな動画で何を見せるべきか、検討してみてください。
多分動画は、二つのパターンに分かれてくると思います。
一つは説明的な動画。もう一つは、映像映えする動画。
この二つではないでしょうか。
どちらにもメリットデメリットがありますが、両方の良いところ取りは、
二兎追うものは一兎も得ずになりかねませんので、避けた方が良いでしょう。
説明的な動画のメリット・デメリット
メリットは、独自性を出しやすい点です。
競合他社との違いを出しやすく、説得や教養を高める方向に向いています。
違いや仕組みに触れやすく、大人、マニア向けで特定の領域に刺さると工場見学の魅力の柱にできる可能性が高いです。
デメリットは込み入った内容になりやすく、ガイドと合わせて使うことが前提で、
ガイドがいない場合、動画としての価値が下がりがち。
映像映えする動画のメリット・デメリット
メリットは、派手で分かり易い点です。
年齢層に関係なく、驚きと満足感を与えやすいのが強みです。

派手さがあるだけで、工場見学全体での緩急を作ることができ、
工場の内容によっては、見せ場としての柱にすることも可能でしょう。
工場見学全体の満足感に影響しやすく、工場の設備をあまり見せられない場合や、体験が少ない場合などには積極的に取り入れて、緩急を作るようにしましょう。
子ども受けも良いのが特徴で、どこか一箇所には、取り入れたい内容です。
デメリットは映像映えを狙う場合、内製化が難しい可能性が高いです。
特殊な撮り方や機材が必要になるケースがあり、制作する場合は外注してしまう方がお得でしょう。
また客観的な視点も必要で、何が映えになるのか現場で働いている人には、ピンとこない可能性があります。
映えが、どこかを見付けるのがそもそも難しい。
テクニカルなものでもあります。
上記の2つを紹介してきました。
それでは、それぞれ一般的な動画の作り方について紹介します。
説明的な動画の作り方
機能や働きを説明する動画です。
ここで大切なのは、プロセスの始まりと終わりをどこに置くかが重要です。
見学ポイントに立ち、どこから説明を始めるか考えてみてください。
そして、前後の見学ポイントにも立ち、どこまでが説明範囲になっているかを考えます。
工場見学動画では、現場で見えていない部分まで説明する必要はありません。
動画はあくまで現場のサポートです。
現場で見ている景色や内容が最高になるように演出するのが仕事です。
ですので、見学ポイントで見えているものをベースに考え、
前後のポイントで説明が重複しないかだけで判断するのが良いでしょう。
実写かアニメーションか
アニメーションが最適です。
説明的な動画は、知識や教養で見学ポイントを演出するのが狙いです。
見学ポイントは実写で見ている景色なのでコントラストを付けるためにもアニメーションの方が効果的です。
アニメーションは、パワーポイントのような図面は避けましょう。
現場を演出するのであれば、機械やラインの模式図で表現し、流れや仕組み、
内部構造の機能などのわかりやすさに重点をおいてください。
現場で見ているものと図解が脳内でリンクするようになることで、
知識を五感で感じ取れるので、体験感が得られるでしょう。
アニメーションはシンプルに
3DCGなど、こだわる必要はありません。
3DCGは緻密でリッチな仕上がりになりますが、
CGは緻密なため、思いのほか大きな画面が必要になりがちです。
小さい画面で機能を伝えるのであれば、2Dアニメーションにするのが伝わりやすいでしょう。
矢印アニメーションは避ける
物事の流れや進行を見せるのに矢印アニメーションを使うのは避けてください。
チープに見えやすく、図の部分を埋めがちで言葉でのテロップでのフォローを入れがちになります。
すると段々と細々なっていき分かりづらいものになります。
機能や名称の説明テロップは最小限に、ターゲットの年齢総やマニアック度にもよりますが、
一般的にはアニメーションのテロップ説明は最小限にした方がいいです。
理由は、動画を見るために来ている訳ではないからです。
細かい説明や補足をし始めると動画尺が長くなりがちです。
実物を見るより、動画の視聴時間が長くなるのならないように設計しましょう。
もし動画が長くなりそうならば、その役目はガイドが一部を担うようにしバランスをとってください。
長い動画を立ちで見させられているのは、苦痛でしかありません。
動画は1分程度まとめる
立ちで動画を見る場合、動画は1分以内にまとめましょう。
1分以上の動画は、苦しくなりはじめます。
そのためにも説明内容はぐっと絞って、良いところだけを説明するようにしましょう。
映像映えする動画の作り方
前述しましたが、映像映えがどこか見付けるのが難しい問題があります。
ですが、その中でも明確になっているものがいくつかあります。
今回は映像映えするもので、確実なものを一部紹介します。
炎
炎は映えます。焚き火が人の心を引きつけるように、
人は炎にどこか神秘的な魅力を感じているのかもしれません。


こういった前置きはおいておいて、工場において炎は特別です。
工場で炎が見られるということは、ある意味で危険な場所と言っても過言ではありません。
工場見学でも安全上の配慮から炎が出る場所は、近付くことが出来ないため、
基本的に見れたとしてもかなり遠くからになってしまいます。
工場の中で見せ場ではあるものの、映えに欠けてしまうのが実情です。
ですので、動画が役立ちます。
炎が間近で見られる動画と組み合わせて、
想像しやすく確実に映えを狙える内容です。
壁、蓋の先
大きな機械、小さな機械が様々工場にはあると思いますが、その中の様子を見ることは現場に来てもできません。
凄い事が音や臭い、温度で伝わって来るのに、鋼鉄の壁に塞がれて分からない。
そういった機器の中の様子は、インパクトがあり映える動画と言えます。
普通にネットで動画を見るのと違い、工場には五感を刺激するもので溢れています。
視覚の部分を動画で補うことで、最もリアルな4DX体験を作りだすことができるのです。


食品加工系には注意
食品加工などでの加工シーンは映え要素が高いですが、
動物などの生き物が加工されるシーンには注意が必要です。
一次加工されたものも同様で肉々しいものは、一度審議した方が良いでしょう。
ガイドがその場で判断できるなど柔軟な対応がとれるような仕組み作りが大切です。
とは言え、このようなシーンは本来教育的価値が高いものだと思いますし、
目を背けることが正しいとも個人的には思いません。
むしろ、慎重な判断が必要な内容だからこそ価値が高いとも言えないでしょうか。
このような動画は、ガイドの力量に大きく影響を受けるものだと感じています。
動画を見せるための前振りや、声音や目力といった、仕切り方によって、
良くも悪くも受け取り方が変わってきてしまうものだと思います。
ガイドの知識や見学案内の上手さによって使い分けてもいいかもしれません。
音はオン、オフ切替ができるように工夫
現場のラインが稼働しているのであれば、音は不要です。
現場の音を活かした方が、動画は映えます。
しかし、現場のラインが稼働していないような時には音はあった方がいいですので、
動画収録時の音が聞こえるような工夫が出来るようにすると良いでしょう。
動画は15~30秒程度
映え動画は、説明には向きませんので、長尺にしておく必要ありません。
ぱっと見せて雰囲気を感じてもらうのがベスト。
ガイドの説明がある場合でも、現場を見てもらいながらの方がリアリティーを感じられて良いでしょう。
工場見学動画はどこまで内製化できるのか
工場見学動画を内製化するのは、簡単ではありません。
内製化で行う場合、工場見学の内容をある程度絞りシンプルなルートを作るところから始めてください。
ルートを計画段階で、難しさを感じている場合は外注を考えましょう。
ある程度見学ルートの設計ができる場合については、映えの動画部分の内製化が可能か検討しましょう。
これらの動画は、簡単かつ、現場の人が一番よく分かっている内容なため撮影のハードルは低いです。
とはいえ、手持ちで撮影するようなことはせず、
しっかりと三脚などカメラを固定して撮影するなど工夫が必要になります。
説明的な動画は、見せ方や演出、構成やアニメーションなど、
内製化すると時間もコストも掛かりやすく、中長期で動画チームを活用するプランや戦略がない場合は
外注してしまう方が、総合的に判断してコスパが良くなります。
さいごに
いかがだったでしょうか。
BtoC向け工場見学動画の作り方のイメージが湧いて来たのではないでしょうか。
とは言え、工場見学動画は工場見学ルートやポイントなど複数の観点から考えて作る内容を決めていくのが良いため、
内製化するのはハードルが高いため、動画の制作会社を検討する方が良い結果となりやすいです。
失敗しないポイントは、どんな動画を作りたいか相談前にまとめておくようにしましょう。
今回の動画でどのようなパターンかイメージ出来たと思いますので、どのパターンの動画よいか決めておくだけでも
失敗する確率を大きく減らせます。
どういった工場見学動画すればよいか分からないといった場合には、
SoranoueCreativeWorksまでご相談ください。
いただいた条件などから、御社にあった工場見学動画のプランなどご提案させていただきます。